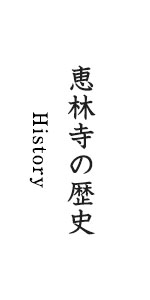武田信玄
Shingen Takeda
第一章〜鍛錬〜
恵林寺は、戦国最強の騎馬軍団を率い、“甲斐の虎”と恐れられた武田信玄(大永元年 1521年~元亀4年 1573年)の菩提寺です。
甲斐武田家第19代当主・武田信玄(諱は晴信、後に出家して機山信玄の法名を授与され、以後信玄と名乗る)は、甲斐国守護・武田信虎の嫡男として生まれました。母は甲斐西郡の国衆で、武田氏一門でもある大井信達の娘で大井の方、大井夫人ともよばれています。
後に晴信の除髪の師匠となって“信玄”の法名を授けることになる名僧・岐秀元伯を自らの在所・大井氏の菩提寺である長禅寺に招き、若き晴信に「四書五経」、「孫子」、「呉子」等を学ばせたのが、この母であったといわれていますから、教育熱心であるだけではなく、自身も優れた教養と見識とを備えていた方だったのでしょう。古長禅寺の寺伝によると、この大井の方は、幼い信玄をつれて甲府の躑躅ヶ崎城館から古長禅寺に通って岐秀に参禅させ、学問と兵法を学ばせた、といいます。戦国を代表する武将・武田信玄の誕生を語るときには、母・大井の方の存在を見過ごすことはできません。
この母の影響もあって、信玄は武人としてだけではなく教養にも優れ、たとえば京都から公家を招いて詩歌会・連歌会を行い、自身も数多くの歌や漢詩を残しています。特に詩歌の道に優れ、その作品が「為和集」、「心珠詠藻」、「甲信紀行の歌」などに収載されています。また、漢詩も嗜み、京都大徳寺の宗佐首座によって「武田信玄詩藁」として編纂されたほどです。
信玄と言えば“風林火山”の旗指物と“孫子の兵法”が思い浮かぶのですが、難解でなる「孫子」を理解実践し、自家薬籠中のものとするためには、幼い頃からのしっかりとした教育と、学びに対する自身の真摯な姿勢がなければ不可能であったことでしょう。
信玄の学問好きについては、「太守訟庭無事官暇の時に逢えば、吾が宗門の碩徳英衲を招いて、道話に日を消すを常となす(明叔録 希庵書状より)」という同時代の高僧の書簡残されており、この書簡にもみることができます。この書簡の書き手は、希庵玄密。信玄は、訴訟ごとや政務の合間に時間ができると、禅宗の高僧・学僧を招いて、終日問答や法話にいそしんだ、というのです。信玄が招き、交流を持った禅僧たちは、たとえば、策彦周良、惟高妙安、岐秀元伯、希庵玄密、月航玄津、天桂玄長、説三宗璨、東谷宗杲、鉄山宗鈍、そして快川紹喜。いずれも名の轟く同時代の高僧ばかりです。
信玄は、最初の禅の師匠ともいえる岐秀元伯に就いて、禅宗の語録「碧巌録」を七巻まで参禅したといいます(甲陽軍鑑より)。「碧巌録」というのは禅の高僧たちの問答や言葉を集めた“語録”とよばれる文献のなかでも代表的なもので、禅宗では「宗門第一の書」とよばれ、内容の深さ難解さで知られています。その「碧巌録」全十巻、百則(ひゃくそく:則は数え方)の公案(こうあん:禅問答)のうち、第七巻まで学び終えたといいますから、これは生半可なことではとてもできないことです。
「ご出陣の間には日々夜々の参禅学道他事なし(甲陽軍鑑より」に記されているように、禅に打ち込んでいるときには戦のおりであっても、昼も夜も、常にひたすら禅に参じていたと言われています。こういう取り組み方ですから、禅僧たちとの「道話」も真摯で厳しく、深いものだったと想像されます。先の書簡の通り、多忙な政務の合間の僅かな余暇に、禅の高僧を招いて一日問答・法話に耽る・・・日常から本格的に禅に取り組んでいた信玄の姿がうかがわれます。
「参禅嗜むべきの事。語に云う、参禅別に秘訣なし、只、生死の切なることを思えと」(甲州法度之次第下巻九十九ヶ条より)これは信玄が家臣たちに対して、禅に打ち込むように指示している部分ですが、禅に参ずる時の秘訣として、禅を学ぶのに何も特別な秘訣などない、ただ、生き死にを切実に感じながら打ち込むのだ、と簡潔に、しかも一番大切な点を衝いて述べているところはさすがというほかはありません。この厳しく鋭い一言に、信玄の禅が凝縮されているようです。
第二章~邂逅〜
武田信玄と禅との関わりを言うならば、すぐさま「心頭滅却すれば・・・」の快川国師とのことになるのですが、信玄と快川国師との関係を見るのであれば、何よりもまず信玄その人の、禅に対する厳しく真摯な姿勢を前提に考えなければなりません。
武田信玄と快川国師はもちろんですが、上杉謙信と天室光育、徳川家康と太原崇孚、伊達政宗と虎哉宗乙のように、戦国の時代、禅僧はしばしば軍師・参謀として武人に仕えましたが、同時に、明日をも知れぬ戦場に生きる武人にとっては、生き死にの問題は深刻で切実であったし、だからこそ執着を断ち切る悟りの道を教える禅僧とは、精神の深いところで結びついていたのです。信玄と快川国師は、この命がけの厳しさにおいて、深く結ばれていたのです。
二人の間には、このようなエピソードが伝わっています(甲陽軍鑑より)。
戦の準備に心を砕く信玄の許に、快川国師から桜の花見の招待が届きます。「恵林寺の両袖の桜が見頃なので、ぜひお越しください」と。戦準備に忙しい信玄は、「帰陣後」までには参りたいと初めは躊躇います。しかし、「花と聞いて行かないのは野暮なことだ」と気を取り直した信玄は、恵林寺に赴きます。満開の桜を堪能した信玄は次のような詩を詠みました。
誘はすは くやしからまし桜花 さねこん頃は 雪のふる寺
あなたにお誘いいただかなかったら、これほどの見事な桜を見逃してしまい さぞかし悔しい思いをしたことでしょう。次の機会に、などと言っていたら、いつの間にか春の桜どころか雪景色になってしまうことでしょう。
このエピソードは、有名な鈴木大拙の「禅と日本文化」の中で紹介されています。そこでは、「さねこん頃は」の部分が「さてこん春は」とされているのですが、信玄公宝物館に所蔵されている信玄の遺したもとの資料では「さねこん頃は」と記されています。さて、資料に忠実に「さねこん頃は」と読むならば、この歌はどう読まれることになるでしょうか。
それはさておき、いくら大切な用事で忙殺されているといっても、いつか、次の機会に・・・などと言っていては、いつの間にか季節は過ぎて、花見どころではなくなってしまいます。散り際の見事さを身上とする桜の見頃は、とても短いのですから。
快川国師は信玄の坐禅の師であり、同時に軍師でもあったのですから、戦準備のタイミングもよくわかっていたはずです。それでも、あえてその大切な時に、花見に招待する。そこには、戦準備よりも大切な「何か」があったはずです。命懸けの戦準備の真っ最中に、花見などと、なんと暢気な・・・しかしそうではないのです。快川国師は、戦準備に忙殺されている信玄に、何か大切なものを忘れてはいないか、戦準備よりも大切なものがある、それをよもや忘れてはいまいな、と問いかけているのです。
花見にやってきて、その「何か」に気がついたからこそ、信玄は「誘はすは くやしからまし桜花・・・」と歌を詠んだのです。信玄のこの歌は、言ってみれば快川国師から出された「公案」に対する答えなのです。
快川国師は、この信玄の答えぶりに、とても満足したのでしょう。だから、国師は「太守桜を愛す蘇玉堂 恵林寺またこれ鶴林寺・・・」と漢詩を作って応じ、恵林寺の僧侶たちも皆、それに詩を作って応えたと言います(甲陽軍鑑より)。
後に国師は、信玄没後、その七回忌にあたっての法語の中で、信玄の桜を詠んだ和歌が「餘音猶在耳」・・・その響きが、今なお耳に残っている・・・と、在りし日の交流を思い起こしながら讃えています(甲恵集より)。国師の問いかけに応えることのできた信玄は、まさしく気力充実、百倍の勇猛さで戦に臨んだことでしょう。ですから、ここは「さねこん頃は 雪のふる寺」は、「次に来るときには雪見を楽しむことに致しましょう」と解釈したい誘惑に駆られます。
快川国師がその見事さ故に信玄を誘い、信玄がその姿を歌に詠んだ恵林寺の桜は、開山 夢窓国師が山門の両脇に植えるように命じ、“両袖の桜(りょうしゅうのさくら)”と名付けたものです。その桜が見事に咲いている間は、恵林寺も栄えるであろうと言うのです。今日、この“両袖の桜”は、代替わりしながらも引き続き同じ場所にあり、夢窓国師の願いと、快川国師・信玄公の思いを今日に伝えています。
第三章〜切迫〜
さて、若き信玄は天文10年(1541年)に重臣たちと共に実父、信虎に反旗を翻して国外に追放します。そして家督を継いで後は諏訪に侵攻し、さらに信濃を平定。「甲州法度之次第(信玄家法)」を定めるなどして内政を強化し、五度にわたる、川中島の合戦など、上杉謙信らとの激しい戦を繰り返しながら、遠江・三河へ侵攻。三方ヶ原の戦いで徳川家康の軍勢を打ち破り、征西して京都を目指すも、この頃より病が悪化。撤退を決め、甲斐に引き返す途上、4月12日、一説によれば三河街道上、信州駒場において、波乱に満ちた生涯を終えました。享年53歳でした。
信玄の遺偈として次のような言葉が伝えられています(甲陽軍鑑より)。
大抵還他肌骨好 不塗紅粉自風流
大抵は他の肌骨(きこつ)の好きに還す 紅粉を塗らざれども自から風流
人の美しさというものは、ほとんどが生まれつきの肌と体つきによるものなのだ。華やかな化粧で飾り立てず、生まれつきの素肌のままでいても、自然にその姿が素晴らしいものとなるのだ。人生を終えるその間際において、自分の境涯を女性の飾らない美しさにたとえて表現する、これはいったいどういうことなのでしょうか。
実は、この言葉は「禅語」、それも生半可な修練ではとうてい出てくることのない第一級の禅語なのです。
女性の美しさは、生まれつきの肌や骨格で決まる、だから、お化粧などしなくても、そのひとその人の自然な美しさがあるのだ・・・この禅語は、そう言います。しかし、そうは言っても、女性は鏡に向かい、頬紅をさし、居住まいを整えます。紅粉は、女の命でもある・・・侍が甲冑と太刀とを身に纏うように、時として女は、紅粉で武装する。“紅粉を塗る”とは、命懸けのことです。そこには、愛憎があり、欲望や野心、夢や希望、絶望や不安、嫉妬や狂熱が存在します。人間の剥き出しの姿があるのです。
侍が武具で身を護り、農夫が鍬や鋤で身を保ち、詩人が紙と筆で身を立てていくように、誰もが何らかの形で生きていくための鎧を身に纏う。女性の“紅粉”は、その象徴です。
天下一の“百万石の槍”が世に喧伝されるように、人間の功績は、そうした武装によって達成され、評価される。刀や槍が、お金に替わり、甲や甲冑がスーツに替わっても、同じです。しかし、敢えてそこをこの禅語は「紅粉を塗らざれども自から風流」というのです。「紅粉」を塗ることもなく、太刀を手に取ることも、自分の得意の得物を手にすることもなく、素っ裸で、無防備の姿をさらす・・・地位名誉も、肩書きも、名前も勲功も、すべてかなぐり捨てて。しかし、人が死ぬときには、誰もがそうなるのです。どれほど優れた能力があり、並外れた業績を残した人間であっても、最期にはこの身一つで死んでいくのです。生まれてきたときと同じく、一糸纏わぬ素っ裸になってこの世を去るのです。それを「自から風流」なのだと、この禅語は語りかけています。
死期を悟った信玄は、重臣の山県昌景や馬場信春、内藤昌秀らに後事を託し、山県に対しては「源四郎、明日は瀬田に(我が武田の)旗を立てよ」と言い残したといいます(甲陽軍鑑より)。強敵との戦に明け暮れながら、知略を尽くして戦国最強と恐れられた軍勢を育て上げ、宿敵を倒して都への道が目前になったところで、病のために断念をしなければならなかったその生涯・・・そこに無念がないといえば嘘になります。しかし、そこにおいてこそ、自らの運命を引き受ける透徹した眼が生きてくるのです。
赤子のように、生まれたままの、そのままの存在を、禅の世界では「娘生(じょうしょう)」と言います。赤子は、無心で、無垢です。しかし、生まれたまま、ありのままの「娘生」では、人生を全うすることはできません。
かつて信玄は、このような訓言を遺しました(甲陽軍鑑より)。
「凡そ軍勝五分を以て上となし、七分を以て中となし、十分を以て下と為す。
その故は五分は励を生じ七分は怠を生じ十分は驕を生じるが故。
たとへ戦に十分の勝ちを得るとも、驕を生じれば次には必ず敗るるものなり。
すべて戦に限らず世の中の事この心掛け肝要なり」
戦というものは、五分と五分であれば、上々。七分三分で優勢であれば、中程度。十分で圧勝するならば、結果は下だと考えなさい。なぜならば、五分五分の互角であれば、次こそはと励みが生まれる。しかし、七分の勝ちであれば油断が生じて怠けが始まる。そして、百パーセント勝ってしまえば、驕慢、傲りを招くからだ。戦で完勝しようとも、驕慢を生じてしまえば、次には必ず負ける。戦に限らず、世の中のことは、すべてこうだという心がけが肝心である。
厳しい戦乱の世に、国主として領民を護り導かなければならなかった信玄には、負けることは許されませんでした。小さな戦の勝ち負けにこだわり、大局を忘れるならば、必ずその国は滅びることでしょう。前線での戦闘と同時に、郷土の将来を大きな視野から見据えて戦い続けた武将ならではの、優れた洞察がこの訓言には光っています。そして、生涯の最期には、勝ち負けも、名誉も、栄枯盛衰をも越えたところで、「紅粉を塗らざれども自から風流」兜も、鎧も、太刀も、知略も軍配も捨てて、一糸纏わぬ素っ裸になって、生まれてきた生命の根源に帰って行くのです。
過酷な時代の現実のただ中を全力で駆け抜けた、傑出した人間の眼は、人生の、あるいは歴史そのもののはるか彼方まで、向けられていたのでしょうか。